2008年10月15日
かえるで〔大阪弁ではないよぉ~ん〕
秋が深まってくると
日本では、紅葉を見物する行楽、紅葉狩り(もみじがり)に
出かける人が多いのでは
「狩り」というのは「草花を眺める事」の意味です
紅葉〔もみじ〕は 楓が紅葉すると もみじといいます
楓は かえるの手という言葉のなまりからきているそうです
ほんとそう言われると
かえるの手に似てますよね
かえるで かえるでと言っている間に
『かえで』って呼ばれるようになったと言う事です
着物にも楓の文様が多く使われてます
染織文様として使われたのは 桃山時代からだそうですよ
日本では、紅葉を見物する行楽、紅葉狩り(もみじがり)に
出かける人が多いのでは
「狩り」というのは「草花を眺める事」の意味です
紅葉〔もみじ〕は 楓が紅葉すると もみじといいます
楓は かえるの手という言葉のなまりからきているそうです
ほんとそう言われると
かえるの手に似てますよね
かえるで かえるでと言っている間に
『かえで』って呼ばれるようになったと言う事です
着物にも楓の文様が多く使われてます
染織文様として使われたのは 桃山時代からだそうですよ
2008年10月10日
10月10日
今日は とてもよいお天気でしたね
10月10日はそもそも お天気の現れる傾向が多い特異日だそうです
スポーツの秋っていったところでしょうか…
それと もうひとつ
「10を二つ並べて横にしたときに、眉と目の形に見える」ことから、
今日は目の愛護デーだそうです
長時間パソコン画面に向かって仕事をしているので
目の疲れや眼痛などを引き起こしやすいので
目を少し休めてあげないとだめですね
パソコンが手放せないという人は注意して下さいね
10月10日はそもそも お天気の現れる傾向が多い特異日だそうです
スポーツの秋っていったところでしょうか…
それと もうひとつ
「10を二つ並べて横にしたときに、眉と目の形に見える」ことから、
今日は目の愛護デーだそうです
長時間パソコン画面に向かって仕事をしているので
目の疲れや眼痛などを引き起こしやすいので
目を少し休めてあげないとだめですね
パソコンが手放せないという人は注意して下さいね
2008年10月08日
寒露
10月8日頃~霜降までを 二十四節気では寒露
寒露(かんろ)は、ぼつぼつ露が冷気によって凍りそうになるころ。
雁などの冬鳥が渡ってきて、菊が咲き始め、
蟋蟀(こおろぎ)などが鳴き止むころ。
いよいよ 秋が深まって行く頃ですよね
寒露(かんろ)は、ぼつぼつ露が冷気によって凍りそうになるころ。
雁などの冬鳥が渡ってきて、菊が咲き始め、
蟋蟀(こおろぎ)などが鳴き止むころ。
いよいよ 秋が深まって行く頃ですよね
2008年10月06日
乾杯のマナー
乾杯は お互いの健康と 繁栄を祝して します
お酒をついでもらうときは グラスをもったり
テーブルに置いたまま 手を添えたりしません
全員にお酒がつがれたら
右手でアンダーバストの位置に持ち
「乾杯」で 目の高さまで上げ
アイコンタクトで 一口飲みます
グラスを合わせて 音をたてません
昔 魔を除けるために 音をたてたそうですが
器が繊細になったので 音をたてなくなりました
アイコンタクトをしながらの 「乾杯」は
お互いの 心が通うように思われます
お酒をついでもらうときは グラスをもったり
テーブルに置いたまま 手を添えたりしません
全員にお酒がつがれたら
右手でアンダーバストの位置に持ち
「乾杯」で 目の高さまで上げ
アイコンタクトで 一口飲みます
グラスを合わせて 音をたてません
昔 魔を除けるために 音をたてたそうですが
器が繊細になったので 音をたてなくなりました
アイコンタクトをしながらの 「乾杯」は
お互いの 心が通うように思われます
2008年10月06日
出雲大社 神在祭
出雲大社では ニ拝四拍手一拝だそうです
日本中の 神様が 出雲に出張なさっているので
神在祭には 大勢の参拝者で にぎ合うようですよ
縮緬の技法は 安土桃山時代の後半に
中国(明)より 伝えられましたが
羽二重は 明治の始め頃から 技術研究が始まり
明治20年頃には 技術の基礎が 確立した
日本特産の 織物です
主に 胴裏 八賭け 長襦袢等の裏関係に
また 男物の紋付や 女物の喪服にもつかわれます
「ぬれよこ」呼ばれる 緯糸を水で湿らせて 織るので
糸が締まり 極上の つるつるとした 美しい風合いになります
鳥の羽のような ふあっとした下風合いと
経糸を 2本引き揃えて 織ることから
「二重」という意味にとり 「羽二重」と言われるそうです
日本中の 神様が 出雲に出張なさっているので
神在祭には 大勢の参拝者で にぎ合うようですよ
縮緬の技法は 安土桃山時代の後半に
中国(明)より 伝えられましたが
羽二重は 明治の始め頃から 技術研究が始まり
明治20年頃には 技術の基礎が 確立した
日本特産の 織物です
主に 胴裏 八賭け 長襦袢等の裏関係に
また 男物の紋付や 女物の喪服にもつかわれます
「ぬれよこ」呼ばれる 緯糸を水で湿らせて 織るので
糸が締まり 極上の つるつるとした 美しい風合いになります
鳥の羽のような ふあっとした下風合いと
経糸を 2本引き揃えて 織ることから
「二重」という意味にとり 「羽二重」と言われるそうです
2008年10月01日
神無月
陰暦の十月のことを神無月といいます。
これは全国の神々が出雲の国に集まられ、神々が留守になるからだそうです
反対に出雲では、神々が集まるので「神在月(または神有月)」
というそうです
出雲の国は、神の国、神話の国として知られています。
その“出雲の国”の中心が「大国主大神(おおくにぬしのおおかみ)」
をおまつりする出雲大社(いづもおおやしろ)です。
全国から神々をお迎えして会議をなさるのだという
信仰が生まれたと考えらるそうです。
他に 新米で酒をかもす「醸成月(かみなしづき)」、
雷の鳴らない「雷無月(かみなしづき)」の意味もあるとか
今日は お茶のお稽古
お稽古も十月に入り
設えが変わりました

かきあげ灰

茶花は
ススキ(おばな)
桔梗
りんどうです
これは全国の神々が出雲の国に集まられ、神々が留守になるからだそうです
反対に出雲では、神々が集まるので「神在月(または神有月)」
というそうです
出雲の国は、神の国、神話の国として知られています。
その“出雲の国”の中心が「大国主大神(おおくにぬしのおおかみ)」
をおまつりする出雲大社(いづもおおやしろ)です。
全国から神々をお迎えして会議をなさるのだという
信仰が生まれたと考えらるそうです。
他に 新米で酒をかもす「醸成月(かみなしづき)」、
雷の鳴らない「雷無月(かみなしづき)」の意味もあるとか
今日は お茶のお稽古
お稽古も十月に入り
設えが変わりました
かきあげ灰
茶花は
ススキ(おばな)
桔梗
りんどうです
2008年09月30日
マナー講師

月の2回 マナー講師の研修を行い
知識の確認と技術の向上をはかってます
いつも思うことは
日々勉強
特に動作は
頭でわかっていても
すぐに出来ません
基本的な事を学び
それを知恵にかえ
時と場合にあった動きが自然に
出来るようになります
そうして皆さん講師として
活躍されてます
2008年09月29日
台風
台風15号が 接近しているようです
前回の14号と 同じコースを
たどっているようで 台北では大変な事になっているようですね
日本にも直撃とか…
大きな被害にならなければ良いのですが
自然に猛威には 人間の力では
どうしょうもないですよね(>_<)
台風って 日本では、古くは野の草を吹いて分けるところから、
野分(のわき、のわけ)って言ったそうです
これは 枕草子なんかにも この様に表現されているそうです
その後、明治時代頃から颶風(ぐふう)と呼ばれるようになり
現在の台風という名は、
1956年の同音の漢字による書きかえの制定にともなって、
颱風と書かれていたのが台風と書かれるようになったそうです
意外と最近なんですね
その由来には色々な 説があるようです
台風こないで(@_@)ね
前回の14号と 同じコースを
たどっているようで 台北では大変な事になっているようですね
日本にも直撃とか…
大きな被害にならなければ良いのですが
自然に猛威には 人間の力では
どうしょうもないですよね(>_<)
台風って 日本では、古くは野の草を吹いて分けるところから、
野分(のわき、のわけ)って言ったそうです
これは 枕草子なんかにも この様に表現されているそうです
その後、明治時代頃から颶風(ぐふう)と呼ばれるようになり
現在の台風という名は、
1956年の同音の漢字による書きかえの制定にともなって、
颱風と書かれていたのが台風と書かれるようになったそうです
意外と最近なんですね
その由来には色々な 説があるようです
台風こないで(@_@)ね
2008年09月23日
お彼岸

「暑さ寒さも彼岸まで」とよく言ったものですね
すっかり 涼しく過ごしやすくなりましたよね
今日は秋分の日 お彼岸です
お彼岸は 秋分の日(春分の日)を真ん中にして
前後3日間を彼岸と言うそうです
お彼岸を迎えるころには厳しかった暑さ寒さも和らぎ、
とてもいい季節を迎える頃です
春のお彼岸には牡丹餅、
秋のお彼岸にはおはぎを食します
春は牡丹の花が咲く頃で 牡丹餅
秋は萩の花を見立てて おはぎとし
先祖のお供えをします
中のもち米がつぶつぶで つぶあんが牡丹餅
中がお餅でこしあんがおはぎと思っていたのですが
地方によって色々のようです
何がともあれ
先祖を敬う事は とても大切なことですよね(*^.^*)
2008年09月16日
敬老の日

昨日は敬老の日でしたよね
敬老の日って調べてみると
発祥は兵庫県なんですって
昭和22年
『としよりの日』が始まりだそうです
そもそも
老人を大切にし、年寄りの知恵を借りて村作りをしようが
始まりだそうです
昭和25年頃から 兵庫県全体に広がり
後に全国ネットになったそうですよ
2008年09月07日
2008年08月12日
精霊馬

精霊馬(しょうりょううま)=キュウリとナス■
キュウリとナスビに割り箸を刺してお飾りをする
地域がありますが
これは
キュウリは馬の例えです
少しでも早く迎えられるようにとの願いを表現しています。
ナスは牛を表現しています。
お盆が終わって、帰るときはのんびりという意味を表現しています
◆一説には、
「精霊がキュウリの馬に乗り、牛には荷物を乗せて楽に帰れるように」
という意味が込められているとも言われています。
2008年08月09日
藤森神社
今日はプライベートで京都に出掛けてました
鴨川のほとりでは 納涼祭が行われており
とても賑やかでした
四条から京阪電車で墨染駅で降りて
散策してますと
藤森神社の前を通りました
とても大きく立派な神社で
菖蒲の節句発祥の地と書いてあったので

へぇ~と思い
境内に入ってみることにしました
菖蒲(勝負)の神社ということなんでしょうか
馬の神社でもあり
馬主さんや競馬ファンの方が
多く訪れる 神社でした

思いがけない出来事で
わくわくしながら
神社の中を散策しました
http://www.fujinomorijinjya.or.jp/
鴨川のほとりでは 納涼祭が行われており
とても賑やかでした
四条から京阪電車で墨染駅で降りて
散策してますと
藤森神社の前を通りました
とても大きく立派な神社で
菖蒲の節句発祥の地と書いてあったので
へぇ~と思い
境内に入ってみることにしました
菖蒲(勝負)の神社ということなんでしょうか
馬の神社でもあり
馬主さんや競馬ファンの方が
多く訪れる 神社でした
思いがけない出来事で
わくわくしながら
神社の中を散策しました
http://www.fujinomorijinjya.or.jp/
2008年08月02日
風鈴
夏の風物詩といえば 風鈴
最近クーラーを入れる家庭が多く
風鈴のチリン♪チリン♪
音が聞かれなくなりましたよね
風鈴の祖先は風鐸(ふうたく)というものです。
中国由来のものですが、
日本の古い寺院や塔などでも軒下四隅に吊されています。
本家中国での 風鐸は占いや儀式に用いたようですが、
日本ではどちらかというと 厄除けとして見られたようです。
昔、風鐸に限らず鳴物は魔除けの効果が あると信じられていたそうです。
有名なところでは宮中や貴族の出産などで 行われた
「鳴弦(めいげん)」
弦をはじいて鳴らす、その音で 悪いものを追い払ったんですよね
そういえば、今でもお守りや絵馬などには鈴がついているものが多いですよね。
これも魔除けの意味があるんですよね

我が家の風鈴は
少し風物詩から離れているかもしれませんが
ぷーさんです
なかなか 音は涼しげなんですよ(*^.^*)
最近クーラーを入れる家庭が多く
風鈴のチリン♪チリン♪
音が聞かれなくなりましたよね
風鈴の祖先は風鐸(ふうたく)というものです。
中国由来のものですが、
日本の古い寺院や塔などでも軒下四隅に吊されています。
本家中国での 風鐸は占いや儀式に用いたようですが、
日本ではどちらかというと 厄除けとして見られたようです。
昔、風鐸に限らず鳴物は魔除けの効果が あると信じられていたそうです。
有名なところでは宮中や貴族の出産などで 行われた
「鳴弦(めいげん)」
弦をはじいて鳴らす、その音で 悪いものを追い払ったんですよね
そういえば、今でもお守りや絵馬などには鈴がついているものが多いですよね。
これも魔除けの意味があるんですよね
我が家の風鈴は
少し風物詩から離れているかもしれませんが
ぷーさんです
なかなか 音は涼しげなんですよ(*^.^*)
2008年08月01日
葉月
今日から8月ですね
8月は 葉月
葉月の由来は色々あるそうですが
木の葉が紅葉して落ちる月「葉落ち月」
「葉月」であるという説が有名である。
他には、稲の穂が張る「穂張り月(ほはりづき)」という説や、
雁が初めて来る「初来月(はつきづき)」という説、
南方からの台風が多く来る「南風月(はえづき)」という説などがあるそうです
また、「月見月(つきみづき)」の別名もあります
暦の上では もう秋なんですが
まだまだ 暑い日は続きそうですよね
8月に入った事もあり
夏のご挨拶で毎日お取引先様まわりです(;^_^A

今日は 西脇から 福知山 丹後とまわってきました
緑がとってもきれくて ちょっとした 旅行気分
途中で立ち寄った 道の駅

丹波っていえば やっぱり黒豆パンですよね
8月は 葉月
葉月の由来は色々あるそうですが
木の葉が紅葉して落ちる月「葉落ち月」
「葉月」であるという説が有名である。
他には、稲の穂が張る「穂張り月(ほはりづき)」という説や、
雁が初めて来る「初来月(はつきづき)」という説、
南方からの台風が多く来る「南風月(はえづき)」という説などがあるそうです
また、「月見月(つきみづき)」の別名もあります
暦の上では もう秋なんですが
まだまだ 暑い日は続きそうですよね
8月に入った事もあり
夏のご挨拶で毎日お取引先様まわりです(;^_^A
今日は 西脇から 福知山 丹後とまわってきました
緑がとってもきれくて ちょっとした 旅行気分
途中で立ち寄った 道の駅
丹波っていえば やっぱり黒豆パンですよね
2008年07月28日
白雨
今日はすごい雷雨でしたね
真っ暗になって
被害にあわれた方も
たくさんいらっしゃるようで
お悔やみ申し上げます
夏の夕立の事を白雨(はくう)っていうんです
激しい雨が地を打つ飛沫の彼方に
夏の陽射しが白く透けて見えるような雨のこと。
「しらさめ」ともいいます
今日の雨は そんな浮流なこと
いってられませんよね
なぁ~か 最近変ですよね(-_-#)
2008年07月24日
お中元
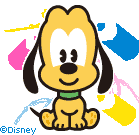
お中元って(^^)o
そもそも天神を祭った「三元」の日「上元、中元、下元」
がそれぞれ陰暦の一月、七月、十月 の十五日にあたり、
特に中元は善悪を判別し、人間を許す、神を祭る日とされてきました
それが、仏教の「盂蘭盆会」(お盆)
の行事と結びついて日本で広まりました
1年の上半期の区切りの意味で、
商い先やお世話になった人に贈答品を贈る習慣
ができたようです
関東では 中元は旧暦の7月15日に行われた行事でした。
現在では旧暦ではなく新暦(現在の暦)
7月15日の頃に贈るならわしとなり
7月上旬~15日頃に送ります
関西ではお盆のお供えにと
7月中頃~お盆までに送るとされてます
地域によって 違うんですね(*^.^*)
2008年07月23日
大暑

7月23日頃から 二十四節気では 大暑(たいしょ)です
7月23日から立秋(8月7日頃)までの期間
1年で一番暑い時期ですよね
太陽黄経が120度のときで、
快晴が続き気温が上がり続けるそうです
夏の土用が大暑の数日前から始まり、
大暑の間中続きます
小暑と大暑~立秋 1ヶ月間が暑中で、
暑中見舞いはこの時期に送ります
メールもいいけど
ご無沙汰している 知人に
暑中見舞いを送ってみてはいかがでしょうか(*^.^*)
2008年07月20日
土用入り
今日も 暑い一日でしたね
今日は神戸でお仕事
今日は着物を着て外に出ると
さすがに 汗がどばぁ~と
出ました
日傘をさして外を歩くと
日傘を通して
日差しが入ってきましたよね
しばらくは この暑さ続きますよね(;^_^A
7月19日 土用入り
こんなに暑いのに
秋の土用入りです
旧暦なので 季節はずれてます
立秋の18日前から
陰陽五行説で土用の入りです
五行説による季節の割り振りで四季に配当
冬は水、春は木、夏は火、秋は金とされ
「土」の支配する時期を各季節の末
18日ないし19日間を指します
夏の土用の丑の日にうなぎを食べる事が
あまりにも有名なので
夏だけに土用があるようですが
季節の終わり18日ぐらいのことを土用っていうそうです
なぜ うなぎ
江戸時代に暑い夏にうなぎが売れなくて
土用の丑 どようのうしにうなぎを食べ
ようと言ったところ
ばか売れして
その時からうなぎの日になったようですよ(*^.^*)
地方によれば 『う』のつく物を食べるとよいと
されている所も あるそうです
たとえば、うどん・梅干 など…

JR元町駅前
信号を待つときは 日陰で
これって 夏の鉄則ですよね
今日は神戸でお仕事
今日は着物を着て外に出ると
さすがに 汗がどばぁ~と
出ました
日傘をさして外を歩くと
日傘を通して
日差しが入ってきましたよね
しばらくは この暑さ続きますよね(;^_^A
7月19日 土用入り
こんなに暑いのに
秋の土用入りです
旧暦なので 季節はずれてます
立秋の18日前から
陰陽五行説で土用の入りです
五行説による季節の割り振りで四季に配当
冬は水、春は木、夏は火、秋は金とされ
「土」の支配する時期を各季節の末
18日ないし19日間を指します
夏の土用の丑の日にうなぎを食べる事が
あまりにも有名なので
夏だけに土用があるようですが
季節の終わり18日ぐらいのことを土用っていうそうです
なぜ うなぎ
江戸時代に暑い夏にうなぎが売れなくて
土用の丑 どようのうしにうなぎを食べ
ようと言ったところ
ばか売れして
その時からうなぎの日になったようですよ(*^.^*)
地方によれば 『う』のつく物を食べるとよいと
されている所も あるそうです
たとえば、うどん・梅干 など…
JR元町駅前
信号を待つときは 日陰で
これって 夏の鉄則ですよね
2008年07月15日
ちまき
ちまきって言ったら
五月の節句に食べる
おいしいちまきを
イメージされる方が多いと思いますが
京都でちまきと言えば
祇園祭の鉾の横で売っている
ちまきです
これは
八坂神社に祀られている御祭神の素戔鳴尊(すさのおう)
の逸話にこのようなお話があります。
素戔鳴尊が高天原から南海地方に降りられた時、
一夜の宿を求めた時に
途中に蘇民将来(そみんしょうらい)と
巨旦将来(こたんしょうらい)の兄弟の家がありました
巨旦は豊かな暮らしをしていたが宿を断り、
蘇民は貧者であったが喜んで宿を提供しました。
それを喜んだ素戔鳴尊は、
これからもし病気が流行った時には
「蘇民将来之子孫也=そみんしょうらいのしそんなり」
と記した護符を持った者だけは、病気に罹らない様にする、
と約束をした。という故事から来ているそうです
いつしか巨旦将来の子孫は絶え、
蘇民将来の子孫はいつまでも栄えているといます。
この『蘇民将来子孫也』は、ふりかかる災厄から
御祭神素戔鳴尊にお護り頂く言葉として現在に伝わっています。
そのような素戔鳴尊の逸話に習い、厄除け、病気除けの願いを込めて
祇園祭は行われているのです
食べれないよ(*^.^*)
玄関の横に飾って 厄除けをします
京都の軒下でよく見られますよ(^O^)vo

